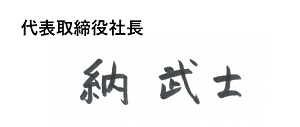ダイバーシティ&インクルージョン実現に向けたトップメッセージ

これだけ変化の激しい時代を迎えました。
かつては想像もできなかったことが
世界中で次から次へと起こっています。
そのような中、この2024年、
私たち三井金属は、創業から150年という
大きな節目を迎えることができました。
この長きにわたる間、当社が事業を続ける
ことができましたのには、理由があります。
その理由と、これからも大事にすべき価値観と
共有すべき想いを、私たちのパーパスに
込めています。
次の50年、次の100年も
世の中に貢献し続けるために、一日一日
スピード感をもって歩みを進めています。
【パーパス】
非鉄製錬を営む上で不可欠な原材料である鉱石を見つけ出す、資源探索から受け継がれています 「探索精神」 は、長い歴史の中で培われた私たちのDNAとも言えるもの、熱意、想いを保ち続け、不確実性の高い状況の中にあっても着実に成果を生み出す力です。
資源開発や製錬事業から派生した 「多様な技術の融合」 とは、非鉄金属素材を知りつくした知識、知見と経験、即ち私たちの 「マテリアルの知恵」 を活かすことで、時代のニーズ、世の中の要請に応えながら、新たな価値を創造していくことです。
この 「探索精神と多様な技術の融合」 とは、「知の探索」と 「知の深化」 を同時に実現する、まさに両利きの経営、そのものでもあります。
「知の探索」、研究開発と市場共創を担っています事業創造本部では、新たな事業の持続的な創造を叶えるべく、事業機会の探索力、研究開発力の強化を図り、事業化推進のフェーズにある開発テーマについては環境の変化に応じてタイムリーに投資と人員の投入を実行しています。
これまでに培ってきました非鉄金属素材に関する私たちの知識、技術を大切にし活かすとともに、足りないもの、さらに必要なものは、社外の既存知を用いるべく CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)によって積極的に出資し、協業、協働を進めています。
両利きの経営におけます、もう一方の 「知の深化」 については、2030年における当社にとって“魅力的な市場”であるエレクトロニクス、環境・資源・エネルギー、モビリティ、さらにはサーキュラーエコノミーの市場それぞれに対応できるよう、一昨年度に事業組織の組替えを行ない、事業部門間での新たなシナジー創出を図っています。また、事業ポートフォリオの動的管理も継続し、価値の拡大・価値の育成の事業では計画的な投資を続け、価値の再構築事業では社内外のベストオーナーの探索を引き続き進めています。
深化によって各事業を改善しつつ拡大させつつ、獲られたそのキャッシュを探索へと投入していくこのサイクルは、しっかりと堅持し、新たなイノベーションへとつなげていきます。
そして、パーパスにあります 「地球を笑顔にする。」 とは、統合思考経営の実践にほかなりません。私たちにとって最大のステークホルダーとも言える地球環境への配慮、貢献です。
私たちが有する知恵を活かし、製品、事業によって経済的価値を生み出すのみではなく、アウトカムとして世の中の環境課題、社会課題の解決にも貢献する。その大前提として、私たちの事業が世の中に、環境に及ぼす 「機会」 と 「リスク」 の掌握も欠かせません。この機会とリスクへの認識をもとに、12項目からなるマテリアリティを特定し、年度ごとにサイクリックに各取組みの進捗を図っています。
気候変動への対応では、当社グループの主力事業である銅箔や金属事業はエネルギー多消費型でありますがゆえに、2050年のカーボンニュートラル実現へ向けての技術的課題、ハードルはけっして低くはありませんが、取組みのステップを着実に進めています。
2023年度は、製錬プロセスにおけるCO2分離回収装置の導入、石炭に替わりますバイオマス燃料の実用性を検証することができました。
環境課題、社会課題の解決に貢献する製品を創出するための検証方法としてLCA、ライフサイクルアセスメントの全社導入も引き続き進めており、2023年度には認定組織を社内に立上げ、当社グループの環境貢献製品のラインナップも整い始めています。
水の管理、環境負荷物質と廃棄物の削減と管理も引き続き強化しています。これらは、当社グループが有する知恵と技術で循環型社会の構築に貢献できる、攻めの取組みでもあります。それぞれの使用量、排出量のとくに大きい金属事業を中心に打ち手を展開していきます。人権の取組みでは、デュー・ディリジェンスの実施を継続し、特定されたリスクに対しては速やかに是正措置を講じています。サプライチェーンの取組みについては、すでに実行のサイクルを確立していますが、引き続き、環境、社会、そしてガバナンスの点で、私たちのサプライチェーンの中にリスクが潜んでいないか、その精査と是正を重ねていきます。当社グループ内はもとより、サプライチェーン全体で様々なリスクを低減し、健全なものとすることは、「地球を笑顔にする。」 ことに資するものとの理解です。
当社グループの競争力を高めるとともに、社会の公器としての企業のあり方を考え、
社会から預かった“人”をはじめとする資本をより付加価値のあるものに変えて社会に還元していく。
私たちグループの企業価値向上の推進力の源泉である非財務資本の充実、強化にも引き続き注力しています。中でも最も重要な資本は“人”です。「経済的価値の向上」 と 「社会的価値の向上」 の両立による統合思考経営を推し進めるために、最も重要な経営資源である人的資本の価値を最大化することが欠かせません。
今も、そして将来も、多様な人材がより活躍できることを目指し、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの取組みを深化・加速させるために、専任組織であるダイバーシティ推進室を2021年に設置し、多様な価値観を持つ全ての従業員が活躍できる職場づくりを実現するための計画を策定、実行しています。
具体的には、中期経営計画における重点取組み項目である 「働きがい改革」 と、多様性を高めて活かす取組みの第一歩として 「女性活躍」 を推進し、多様な人を惹きつける職場の実現を目指しています。また、私が委員長を務めていますダイバーシティ推進委員会では、方針・施策を定期的に協議・決定し、実行状況を管理し、そして課題や委員会での取組み進捗について取締役会への報告事項とすることで、経営方針に沿ったダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進、施策の浸透と定着を図っています。
今年4月には、人事部の中に 「働きがい改革推進室」 を新たに創設いたしました。
働く従業員皆さんのエンゲージメントをさらに高めるとともに、多様な人を惹きつける“場”を構築して企業価値向上へとつなげていく。全社での戦略として、「働きがい改革」 を加速させていきます。
2022年度から導入しています新たな人事制度は、これまでの ヒト基準の人事制度から、職務・役割基準の「ジョブ型人事制度」 へと改め、実力重視の適材適所の配置を図るものです。人生100年時代を見据えつつ、働く一人ひとりが自らのキャリアを自律的に考えることを促すとともに、その実現と成長を支援するため、教育体系をはじめとした体制も整えています。
既に当社の定年年齢を65歳へ引き上げていますが、定年延長にともなって処遇を下げることはいたしておりません。豊かな経験とスキルを有する人材に、引き続き意欲をもち続け活躍していただきたいと願うことからです。
当社グループに働く全ての従業員とその家族が心身ともに健康であることも、重要な経営課題であると認識しています。
これら皆さんが健康であることは、それぞれの生活を充実させ、その個性と能力を最大限に発揮できる基盤となり、会社にとっても生産性を高め、イノベーション創出のためにも欠かせない前提と考えています。
安全第一、この言葉が揺らぐことはありません、職場における災害撲滅が最優先であることは変わりありません。安全で衛生的、健康的な職場環境を整え、健康経営にも積極的に取り組んでいきます。
事業を継続的、持続的に成長させていくために、これら人事マネジメントと経営戦略とを連動させる取組みもたしかに、怠りなく進めています。
2022年に設けました人事ビジネスパートナー室を中心に、本社部門、各事業本部にも担当者を配し全社での連動、連携の体制を整え、全社視点における事業ポートフォリオの動的管理に紐づく人材アロケーションの実行など、先見性のある人事課題を特定し、課題解決のための施策をスピーディに展開し、サクセッションプランや個人別の配置育成計画により各部門でのタレントマネジメントをサポートしています。
まさに、私たちがこれまで培ってきました知恵を権利化し、その保護を図るものであり、知の探索にも深化にも役立つものとして、知的財産マネジメントも積極的に推し進めています。
本社知的財産部でそれらを適切に管理するのみならず、経営企画部や事業創造本部、各事業本部にも知的財産担当者を配し、各部門のニーズに則したスピード感ある知的財産活動を展開しています。専門性の高い知財人材の育成を進めるとともに、当社グループが有します特許価値の拡大を図ることができています。
研究開発のスピードアップ、スマートファクトリー実現、業務の徹底的な効率化のために、DX、デジタルトランスフォーメーションも推し進めています。システムの安全性を高めるとともに、各指標の管理、意思決定のスピードと情報の流れを加速させることに寄与するものです。
昨年度は、いくつかの事業拠点で新たなデータシステムを導入するなど、各事業本部でのDX取組みを進められました。また、経済産業省が選定する 「DX認定事業者」 の認定を得ています。
世の中の流れを追うのではなく、仕組みありきでもありません。
たしかな実効性を求めての移行です。
本年6月開催の定時株主総会でのご承認を経て、当社三井金属は、監査等委員会設置会社へと移行いたしました。
「取締役会での審議件数が毎回多いのではないか」「事業ポートフォリオを踏まえた戦略実行に関する議論にもっと時間を割くべき」「人的資本や知的財産への投資など、経営資源の配分に議論の時間を充てるべき」毎年、当社取締役会の実効性を評価、確認いたします中で、取締役会メンバーから上がりました意見、抽出されました課題です。
総じて取締役会の実効性については確保できていると判断しておりましたが、統合思考経営を推し進め、さらに当社グループの企業価値を高めていくためには、事業環境の変化に対応できるより迅速な意思決定、そしてその透明性をより高めることが必要である、と社長である私自身も感じておりましたところです。
この度の委員会設置によって、執行側へ権限を委譲しそれぞれの意思決定のさらなる迅速化を図りますとともに、取締役会における経営戦略、経営方針を中心とした議論、審議を一層充実させ、取締役会の監督機能の強化も進めてまいります。
また、監査等委員会の設置にともない、当社取締役会におけます社外取締役の構成比率が50%となりました。取締役会の議長、指名検討委員会の委員長ともに社外取締役であり、社長として私が不適であると社外取締役の皆さんが判断されれば、いつでも社長を代えられる態勢となったわけです。当社グループの変革を遂げたい、この三井金属をより良い会社にしたい、そう願う私自身の不退転の決意の表れでもあります。
実行、実践することこそが、やはり全て。
さて、終わりました2023年度の業績につきましては、機能材料事業およびモビリティ事業での主要製品の販売
量の増加がありましたが、非鉄金属価格、貴金属価格が下回って推移したことなどにより、売上高は前年度比△0.8%の微減となりました。
損益面では、上記の販売量増加や在庫要因の好転、退職給付費用の減少、営業外収入の増加などにより、営業利益、経常利益とも、それぞれ153.0%、123.8%の増益となっています。
ただ、足下進めております3か年度の中計経営計画の原計画値に対しては、一昨年度に続いて売上、利益とも未達という結果です。
不確実な時代、舵取りの難しい環境がまだまだ続きますが、足下の経営環境を言い訳とすることはできません。経営トップとして、コミットしました計画値に対し、売上、利益とも未達が続きましたことに責任を強く感じております。
2024年度は、私たち三井金属グループがこれからも持続的に価値を創造していくためには必須のプロセスであり、描いたとおりに実際に実行できるかが非常に重要である、と掲げ謳いました3か年度の中期経営計画が最終年度となります。そして、続く次の3か年度の経営計画を策定する年でもあります。
当社グループの 「2030年のありたい姿」 や 「2030年度の業績目標」 を変えるつもりはありません。それが達成できなければ、2050年の私たち三井金属グループは在り得ない、という覚悟にも変わりはありません。
私たちのパーパスを軸として、両利きの経営をバランスよく進め、経済的価値と社会的価値の両軸の経営戦略を実行し、財務と非財務の両面から持続可能な企業となるべく、統合思考経営への変革を遂げていきます。「地球を笑顔にする。」 ために、揺れ動くことなく、これらを確実に進めていきます。
そして、2030年のありたい姿の実現へ、経営トップとして、これまで以上に情報を積極的に発信し、社内外のステークホルダー皆様とのコミュニケーションも進めていきます。
150年という長い歴史の中で当社グループに関わっていただきましたステークホルダー皆様にあらためて感謝、御礼申し上げますとともに、今後とも、より一層のご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。